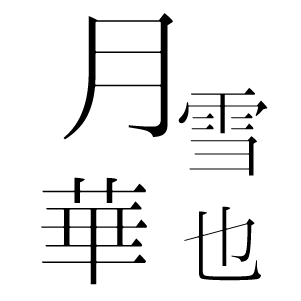――チリン
心地の良い鈴の音が鳴り、店の扉が開いた。分厚いコートを羽織り、フードを目深に被った客が店の戸をくぐる。
青年の横に寝そべる看板犬が気怠そうに頭を持ち上げ、なんと口を開いた。
「あ、久しぶりのお客さんだ……」
「お、おいっ、リリ。喋ったらダメだろ」
慌てた調子で青年、八雲伊綱がリリと呼んだ看板犬の口を押さえる。だが、客の男はそれを見ても驚き一つ示さない。
リリは八雲の手をすり抜けると、軽やかに八雲の元から飛び離れた。
「平気だよ。そういうお客さんなんだから」
振り返り、やはり人の言葉を話す。驚くわけでもなく男はリリを一瞥するのみだった。
「なるほど、コーヒーの注文ではなさそうだ」
八雲がわずかに警戒の目を投げかくるが、目深に被られたフードの下にある表情は伺えない。
男は八雲の前まで歩みを進めると、
「依頼したいことがある。よろしいかな……」
口を開いた。
「ここか……」
目の前にある寺は何処にでもありそうな、だが、寂れた気配のする寺だった。手入れは行き届いているものの、その衰退の気配は隠しようもない。
「妖が妖の密告とは変わった話だね」
「ああ、だが本当なら放っておくわけには行かないからな」
そうリリに答える八雲は喫茶店での和装に加え、長錫杖を携えている。さながら、平安絵巻物から抜け出したような風体だ。
「どうだ、妖の気配はするか?」と八雲は続けた。
先刻訪れた男の依頼は、寺の化け犬が住職に取り付いているから、封じて欲しい、というものだった。
「うん、犬が一匹」
少し鼻をひくつかせ、リリが答えた。
「なるほど、本当だったか」
寺の域内へと入ろうとすると、番犬が激しく吠え立ててきた。
「まさか……この犬のことか?」
何処からどう見ても、威勢の良いふつうの犬だ。
「ほとんど普通の犬と差は無いんだけど、ちょっとだけ妖の気配がするよ。けど、人を呪うには足りないかな」
「そうか……それじゃあ念のために妖の力だけでも封じておくか」
長い錫杖を持ち直し構える。リリも本性を現し、妖犬の姿を見せた。ぴりっと辺りの空気が張りつめる。
犬の鳴き声が一層激しくなり、八雲が動こうとした時、この寺の住職らしい僧が姿を現した。
「おい、君、ウチの太郎に何をしているんだ」
住職はそう叫んだ後、変化したリリの姿を見ると、ぎょっとした顔で、
「な、なんだ……」へたり込んでしまった。
「あれ、僕のこと見えてる?」
素っ頓狂な声を上げ、リリが犬の姿へと戻った。
「犬の姿になった……き、貴様、もしや化け犬か」
住職の混乱する姿を見て、八雲は頭痛のする思いだった。
「厄介なことになったな」
混乱から立ち直った住職が飼い犬をリリから庇うように立っているのを見て、八雲は悩んでいた。
「化け犬……ま、まさか、しっぺい太郎なのか」
そんな八雲の悩む姿をよそに住職は言葉を続ける。
「しかし、しっぺい太郎は伝説かと思っていたのだが」
さっきまでの恐怖など吹き飛んでしまったようにリリをひっくり返す勢いで触る住職。
そんな姿を見て、もしかすると話が通じるかもしれないと考えた八雲は説明を試みた。
「私たちはこちらの犬が貴方に憑いていると聞き、解決のために来たのですが……」
理解されるだろうかと恐る恐る尋ねた八雲だったが、
「太郎が私に取り付く。まさか、そんな、ありえませんよ。確かに、太郎は妖の血を引いているかもしれないですが」
思いの外に、すんなりと返事が返ってきた。
「どういうことか説明していただいても良いでしょうか」
「なるほど、そのようなことが」
昔、人身御供を求める化け猿がいたのだと。地元の村人はそれに手を焼いていたのだが、ある時に通りかかった、僧侶とある犬の活躍により退治されたのだという。
その時の僧侶の子孫が住職で、しっぺい太郎の子孫が飼い犬なのだという。
「さ、お茶のお代わりでもいかがですか」
人の良い笑顔で勧められるお茶を断ることも出来ず、
「どうも、ありがとうございまず」
熱いお茶が湯飲みから湯気を立ち昇らせる。ほのかにお茶の良い香りがした。
「そういえば、少し前までは小猿がよく遊びに来て居ったのですが、最近は見なくなったのですよ」
「小猿ですか?」
ずずっとお茶を飲む住職に対し、熱さに持て余していた八雲は突然の話に相づちを打った。
「ええ、怪我をしているところを助けまして。なかなか太郎には遊ぶ相手が居ませんでしたから、直った後も随分と良く遊んでおりました」
「その猿はどちらから?」
「あちらの山です。昔から好んで人の立ち入る場所ではありません」
「へえ、入らないのですか」
「といいますのも、さっきの話に出てきた、化け物の居た場所だからです」
「なるほど、ありがとうございました」
一気に残っていたお茶を飲み下す。わずかに緩くなっていたが、
「うん。美味しい。ごちそうになりました」
湯飲みを置くと立ち上がった。
「ほら、リリ、行くぞ」
太郎と追っかけっこをして遊んでいたリリが戻ってくる。
「え、もう?」
「ああ、これから仕事だ」
住職の言葉通り、山は人の手がほとんど入っていないようで、荒れ放題だったが、
「どうしてこんな所を行くの」
わずかに道らしい道になっている、獣道を八雲とリリは進んでいた。
道とは言え、ただほんの僅かに開けているのみで、伸び放題に伸びた草をかき分けて進まないといけないような道だ。
「今回の事件は誤情報だった。で、解決じゃないのか?」
「いや、違うよ。今回の事件には裏がある」
「それって、どういうこと?」
「どうして妖が妖かも怪しいような妖をはめようとしたんだ。俺たちに依頼して所で退治はしないのにだ」
「あ、今のダジャレでしょ」
リリが上機嫌で指摘するが八雲は気にせずに続ける。
「最初の依頼者からは隠し切れていない妖気が溢れていた」
「うん、そうだね。捕らえようとしたけど、逃げられちゃった」
「妖である住職の飼い犬とふつうの動物が仲良くできるはずがない。妖はそれ自体が恐れの対象だからな」
「ということは?」
「つまり、一緒にいた猿も妖だったんだろう。そして、依頼主は犬をはめようとしたのではなく、助けようとしたのだと考えればつじつまが合う」
「……どういうこと?」
「さあ、謎解きはここまでだ。黒幕のお出ましだよ」
瞬間、ずんと妖気が辺りに立ちこめる。姿を現したのは大量の猿だった。強烈な殺意が八雲達に差し向けられる。
やや遅れて、巨大な猿が現れた。八雲倍はあるかという体躯に、鉄線のように鋭い体毛が逆立っている。
「どうする、八雲」
やはりな。
多くの妖気に埋もれているが、感じ覚えのある妖気が混じっている事を八雲は見逃さなかった。
「これは、太郎達への復習か?」
ボス猿は八雲達を見下すように鼻で笑うと、
「ああ、そうだ。一族の雪辱をはらすための復習だ。だが、それだけじゃない。人身御供をやめた人間共の目を覚まさせ、我々は復権するのだ」と、高らかに宣言した。
「八雲、どうする? さすがにマズいよ」
「いや、もう少し待て」
きゃん、遙か遠くで鋭い犬の鳴き声がした。
「太郎か」
猿達の間で動揺が走る。
そんな中、八雲は名一杯の声で叫んだ。
「今しかないぞ。復習の連鎖を止められるのは自分しか居ないんだぞ」
八雲の言葉を聞き、息を飲んだ小猿が居た。
「親分……復習ではなく、仲良くは出来ませんか……」
辺りが異様な雰囲気に包まれる中、小猿は言葉を続ける。
「俺……怪我をしているところを、人間に助けられたんです。……だから、復習じゃなくて仲良くも出来ると思うんです」
「ふん、ばかばかしい」
ボス猿は小猿を一瞥することもなく言い放った。
「お前ら、やれ。こんな人間など一ひねりだ」
ボス猿が合図を下す。だが、誰も動かない。
「……」
「お前ら! こんな戯れ言を信じるのか。一族の雪辱を忘れたのか!」
「親分には悪いと思っているけど、昔の敵って言われても、分かんないんすよ。別に人身御供も求めてないし……」
一匹の猿が代表するように、そう答えた。多くの猿達も首を縦に振り、同意を示す。
しばらく黙っていた、ほかの猿達も本音をぽつりぽつりと語り始めた。
「そうか……もう時代は変わっていたんだな……」
衝撃を受けたようにボス猿は言葉を続ける。
「こいつらの先頭に立つには失格だな……もう、後のことは若いものに任せないとな」
そう言って八雲の方へと向き直ると、
「人間、見苦しいところを見せたな」
そう言い残し、山の深みへと去っていった。
一匹、また一匹と猿達は去っていき、最後まで残っていた例の小猿が去ると、八雲とリリだけが残された。
「ねえ、こうなるって分かってたの?」
「さあね、どうだろうか」
そう八雲は答えると、リリの方を向き、
「さあ、早いこと山を下りよう。日が暮れてしまう」そう続けた。